免震設計・制震設計業務の流れ
地震によって建物が大きく揺すられると、その骨組は自らダメージを受け入れながら倒壊を回避するというのが従来の耐震設計でした。しかし1990年頃から、本来の骨組に対して建物と基礎の間に積層ゴム等の免震装置を設け、地震による揺れが直接建物に伝わらないようにした免震技術や、各種の履歴ダンパーや粘弾性ダンパーを付加し、この部分が優先的に地震エネルギー(揺れ)を吸収することにより、揺れの軽減と骨組の損傷回避をする制震技術などが普及してきました。それではこれら「免震設計・制震設計業務の流れ」を見ていきましょう。
1.免震設計・制震設計業務の流れ
免震構造は、建物と基礎の間に積層ゴム等の免震装置を設け、地震による揺れが直接建物に伝わらないようにした構造です。つまり地震によって地盤が激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために、大地震時に構造体が損壊することはほぼ無く、建物が傾くといった地震の被害はほぼなくなります。
制震構造(制振構造)は、建物の構造体に取付けた振動軽減装置(錘やダンパー等)を組み込むことで、地震エネルギーを吸収して、建物に粘りを持たせて振動を抑え、建物の揺れを小さくする構造です。よって耐震構造に比べて揺れを抑えられるため、柱・梁の損傷を防ぐことができます。また上層ほど揺れが増幅することになる高層ビルなどの高い建築物に有効な手段となっています。
これら免震設計・制震設計業務の流れを以下にまとめました。
事前相談
- 1.お問い合わせ
- 電話、メール、FAX等にてお問い合わせ。
- 2.ヒアリング
- ご要望、敷地の状況、予算、スケジュールなどを確認します。
- 3.敷地調査
- 敷地(地盤)を含め周辺状況を既存資料から確認します。特に免震構造を採用する場合は、建物と敷地に水平クリアランス量が必要となります。また液状化の可能性や基礎部周辺の地盤に著しく高低差がないかどうかで設計手法が異なります。
- 4.基本計画提案
- ヒアリングした内容、敷地条件を考慮し、ラフな構造基本計画を提案(構造形式の選定、スパン割と免震・制震部材の平面配置の想定等)します。
- 5.お見積り・工程提案
- 基本計画に基づきお見積りと工程を提案します。
構造設計
- 6.契約
- 契約の締結し、免震・制震設計を開始します。また地盤調査では、通常のボーリング調査に比べて、より地盤特性の把握が必要となるため、PS検層、動的三軸試験 常時微動測定等を必要に応じて内容を指示します(測定ポイント、深度、地盤調査方法等を地盤調査会社と連携しながら進めます)。
- 7.初期打合せ
- ・社内プロジェクト会議
設計担当と図面担当を交えて、⼯程、基本計画時に立てた設計の方向性を共有します。
・お客様とキックオフミーティング
意匠図と基本計画を確認し、事前相談の段階で共有したゴールに進むために、不足している情報を初期質疑としてキックオフミーティングで確認します。 - 8.設計方針決定
- 初期打合せ内容をもとに目標耐震性能を決定します。一般に目標耐震性能は「地震規模」と「設計部位」に分けて設定します。
- 9. 免震・制震部材の選定
- 免震・制震部材の選定では、予備応答性能による性能評価とコスト比較がポイントとなります。選定するためには、幾つかの免震・制震部材のパターンを計画する必要があります。
- 10.予備解析
- 各免震部材の性能を各メーカの性能リストから調べ、予備解析します。この時点で上部構造の部材サイズが有る程度決定している必要があるため、上部構造の水平地震力を仮定し、静的な許容応力度解析を行っておきます。
- 11.免震・制震部材の評価
- 地震応答解析(時刻歴応答解析)を行い、免震・制震部材の応答性能上の特徴を概ね評価します。構造設計上、調整が難しいと思えるシステムはこの時点で外して絞り込みます。
- 12.部材のメーカへ見積調査
- 調査では、以下の点を確認します。
・養生カバー(すべり支承やオイルダンパー)作製を要請
・取り付けベースプレート製作費
・運搬費
・製品の受け渡し方法
・製品検査費
- 13.比較表を作成
- 比較表には以下の事項を記述します。
・免震・制震部材の配置図、部材のリスト(種類、メーカ、基数、主諸元(サイズ、性能))
・予備解析による応答性状(上部構造の設計層せん断力係数、層変形角、免震層変形)
・見積価格(見積条件も併記)
・納まり上の特徴(免震層の高さ、設備機器との緩衝の有無)、メンテナンス上の特徴
・設計者の総合評価
- 14.設計図書の作成
- 設計図書一式を作成します。
- 15.管理者チェック
- 構造計算書及び構造図に相違はないか、または安全性確認に必要な情報が網羅されているか等を管理者がチェックします。
- 16.性能評価(大臣認定)・質疑応答
- 第三者評価機関において「性能評価」受けて国土交通大臣の認定(認定書)を取得します。判定員の質疑に回答します。
- 17.構造設計内容説明
- 免震・制震設計の内容を説明します。建物の構造的特徴や課題クリアのために何をしたか、打合せ通りの設計になっている旨をお客様にお伝えします。
- 18.納品
- 以上の内容に問題なければ確認申請に進みます。
確認申請
- 19.建築確認申請・質疑対応
- 管轄の役所、または民間の審査機関に確認申請を提出(認定書を添付)します。判定員の質疑に回答します。
施工
- 20.施工現場からの質疑対応・現場監理
- 工事開始後、必要に応じて定例打ち合わせに参加し、工事進捗状況、施工内容の確認をします。さらに構造躯体における配筋検査、中間検査、随時工事に立会います。建主様の立場で工事品質の監理し、設計調整を行います。
2.免震・制振建築物が必要な理由
現在、建築基準法は建築物の構造に関する最低の基準として、以下の2つのレベルの耐震性を求めています。
①中地震動に対する財産の保護を目的に、稀に(数十年に一度程度)発生する地震動による地震力に対して構造耐力上主要な部分に損傷が生じないこと。
②大地震動に対する人命保護を目的に、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震動による地震力に対して建築物が倒壊・崩壊しないこと。
これらは基準法の求める最低の耐震性ですが、これを最低の基準としてではなく、満足すべき目標性能として設計されている建物が多くあります。さらに大半の建築物は大地震に対して倒壊・崩壊しないものの損傷を生じるように設計されていることは認識されておらず、基準法に従った建築物でも、大地震に対しても財産が保護されると思われています。
また、要求性能(耐震性能)が低いのみでなく、想定する大地震の大きさも十分ではないことが指摘されています。例えば長周期地震動対策として、既存の超高層建築物等については、自主的な検証や必要に応じた補強等の措置を促すことが定められおり、この対策で示された長周期地震動の大きさは、地域によっては基準法の極めて稀な地震動の 1.5 ~ 2.0 倍と大きなものになっています。
さらに、都市直下型地震による大震災をもたらした 1995 年兵庫県南部地震(M 7.3)以降、2011年3月東北地方太平洋沖地震(M9.0) 最大震度7、2016 年4月熊本地震( M 7.3) 最大震度7など、震度6弱、6強、7の被害地震が頻発しており、こうした地震で記録された地震動は、建築基準法の極めて稀な大地震の強さを上回るものもありました。
以上より、大地震に対する建築物の要求耐震性能の見直しや、想定する大地震動レベルの見直しにより、従来の耐震設計だけでは、対応が難しい状況が生まれつつあります。この状況に対して、有効な対策が免震・制震構造を採用した建築物になります。
コラムの関連記事
-
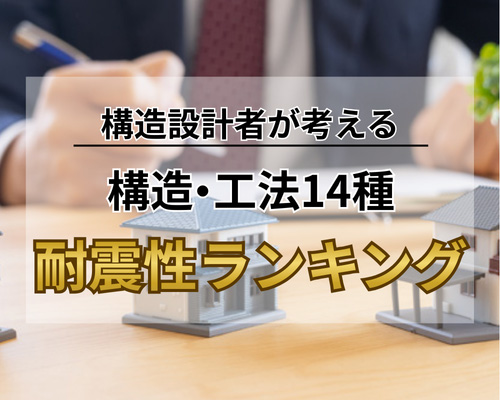
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
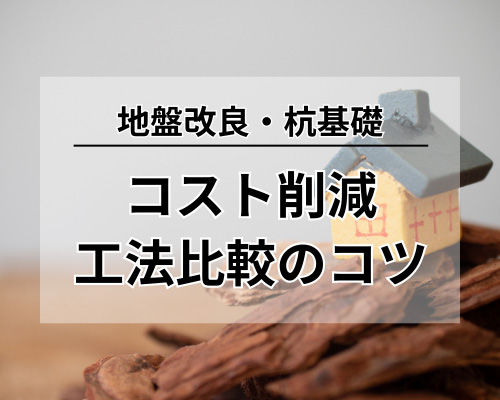
構造躯体最適化
2025年10月01日
構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...
建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...
-

メディア関連
2023年04月18日
メディア取材後の身近な反響
さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...
-

ゼロコスト高耐震化技術
2022年02月03日
構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...
2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...
免制振・動解析の関連記事
-

免震・制震・地震応答解析
2018年04月07日
耐震構造・制震構造・免震構造|耐震性の種類を解説
建物を支える構造形式には建物を強くする「耐震構造」、地震...
-

免震・制震・地震応答解析
2018年03月31日
制震構造(制振構造)とは?制震の仕組みと耐震構造・...
建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造...
-

免震・制震・地震応答解析
2018年03月31日
免震構造の仕組みと耐震構造・制震構造との違い
建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造...
-

免震・制震・地震応答解析
2015年06月23日
長周期地震動について
01はじめに 02長周期地震動とは 03長周期地震動と構...
田中 真一
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
| ●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
|---|
| ●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
|---|
| ●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
|---|



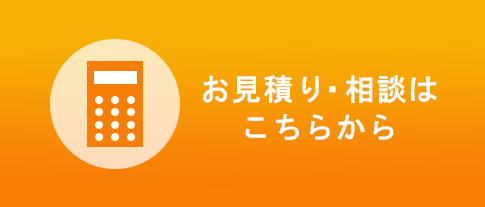

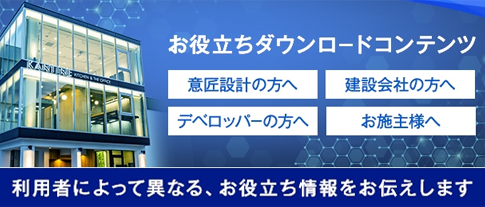
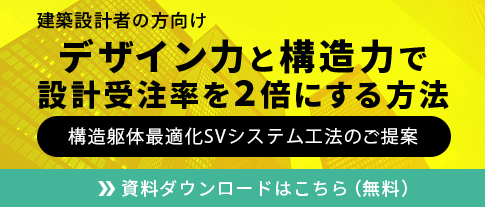
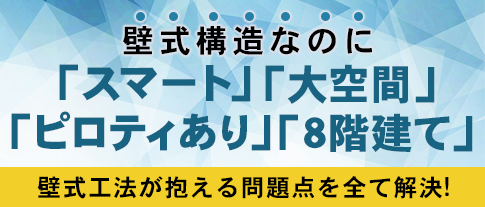
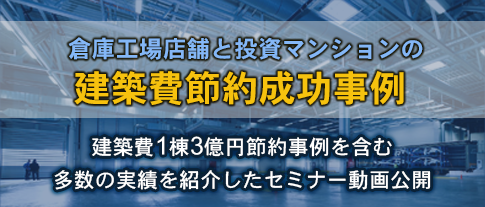
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。