構造計算書とは?
「構造計算書」とは、建築構造物などの構造計算の概要、仮定条件、計算式、試算結果などをまとめた書類のことです。 構造計算書は、一定の規模以上の建築物においては、建築確認申請及び構造計算適合性判定申請時に提出しなければならない書類のひとつでもあります。 それでは構造計算書には、具体的に何が記されているのでしょうか。
この記事では、構造計算書の内容や構造計算書を作成した方がよい一般住宅の条件などについて、詳しくご紹介します。
目次
建物はすべて「構造」によって支えられています。 柱や梁などの「構造」がしっかりしていてはじめて、建物は機能や安全性を維持することができます。 その建物の機能や安全性を確かめる手段が「構造計算」です。
構造計算は、構造設計における重要な業務です。 要求される機能や形を満たした骨組みを考える「構造計画」と、計画した建物がさまざまな荷重を受けた時の状態を検証する「構造計算」の両方が兼ね備わることで、良い構造設計が出来上がります。
構造計算書はこれらの構造計画・構造計算によって作成されています。 構造計算書によって、建築構造物の設計が固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重等に対して安全であり、使用上の支障がないことが確認できます。 そのため、A4用紙で換算するとその量は1,000枚にも及びます。
構造設計業務の一連の流れについて
さくら構造が実際にご依頼を受けた際に、どのような流れで構造設計業務を進めているかは「さくら構造の仕事の進め方」でまとめています。ぜひ、あわせてご覧ください。
1.構造計算書に記載されている内容
建築確認申請及び構造計算適合性判定申請時に提出しなければならない「構造計算書」は、用いた構造計算の種別等によって異なりますが、網羅的に列挙すると以下になります(規則1条の3 表三より抜粋)。
| 構造計算チェックリスト | 使用構造材料一覧表 | 特別な調査又は研究の結果等説明書 |
|---|---|---|
| 基礎・地盤説明書 | 略伏図略軸組図 | 部材断面表 |
| 荷重・外力計算書 |
応力計算書 断面計算書 基礎ぐい等計算書 使用上の支障に関する計算書 |
層間変形角計算書 層間変形角計算書結果一覧表 |
|
保有水平耐力計算書 保有水平耐力計算結果一覧表 |
屋根ふき材等計算書 |
積雪・暴風時耐力計算書 積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 |
|
損傷限界に関する計算書 損傷限界に関する計算結果一覧表 |
安全限界に関する計算書 安全限界に関する計算結果一覧表 |
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 |
|
剛性率・偏心率等計算書 剛性率・偏心率等計算結果一覧表 |
構造計算書の作成にあたっては、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの構造計算が必要になります。 建築構造物によっては構造設計一級建築士の有資格者のみが構造計算できるものがありますが、その有資格者の人数は多くはありません。
上記のように構造計算といっても様々な種類がありますが、一般的な計算方法は「許容応力度計算」です。 その他に一定規模以上の鉄骨造やRC造建物で使われる「保有水平耐力計算」や高層ビル等では「時刻歴応答解析」という方法を使います。
それでは最も使われる「許容応力度計算」による構造計算書を例に見てみましょう。
2.許容応力度計算によって作成される構造計算書の内容
許容応力度計算とは「建物にかかる固定荷重や積載荷重(長期荷重)と地震や台風などの力(短期荷重)を想定して算出した外力(材料等の内部に生じる抵抗力)が、それぞれの部材の許容応力度(限界点)以下であること」を検証する計算のことです。
つまり構造計算は、大きく分けて荷重計算、応力計算、断面算定の三つからなります。 そして荷重設定の妥当性、応力計算のモデル化の妥当性、断面の余裕度など、それぞれの結果を掌握し、建築構造物の全体像をイメージしながら行うことが必要となります。 これらの確認手段として構造計算書が作成されます。
それでは、次に一般的な構造計算書の目次を見てみましょう。
2-1.構造計算書の目次
構造計算書の目次には、おおむねは次のような流れで記載されています。
| 1.一般事項 | まず構造計算概要、構造計算方針、使用材料等を確認します。 |
|---|---|
| 2.構造計算書(1)個別計算編 | 次に設計用荷重を算定し、二次部材(小梁、スラブ等)の算定や基礎の計算を確認します。 |
| 3.構造計算書(2)一貫計算編 | 最後に柱・梁・壁等の構造部材の安全性を構造計算ソフトウエアを使ってチェックします。 |
上の表を見ただけでは想像できないかもしれませんが、構造計算書はA4用紙換算で1,000枚以上になることも珍しくありません。 構造計算を行う構造設計事務所にとっても、建築確認審査機関にとってもチェックするのは膨大な作業量になります。
構造計算について
構造計算についての詳しい解説は「構造設計と構造計算の違いとは?」をご覧ください。
3.法の落とし穴。一般住宅でも構造計算書を作成した方が良い例
構造計算書は、必ずしもすべての建物に必要なものではありません。 建物の種類によっては、構造計算書が不要なケースがあります。 例えば「4号建築物(4号建物)」と呼ばれる木造2階建て住宅では、建築基準法施行令で定める「仕様規定」を満たすことで、構造計算書を作成しなくても建築基準法に定める構造耐力を有している住宅だと認められています。
しかしながら、実際に仕様規定を満たした4号建築物(木造住宅)を構造計算してみると、構造計算上で必要な壁量が不足している4号建築物が存在すると言われています。 また、一般的な住宅であっても、木造3階建て、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の住宅では、構造計算書が必要になるものがあります。
さらに構造的な影響要因が発生しやすい住宅の場合は、デザイン性(建築計画含む)と構造安全性がトレードオフにならないように、構造計算の必要性を確認すべきです。 つまり住宅の構造計算は、法的な観点のみで必要性を判断して良いというわけではないのです。
| 項目 | 構造的な影響要因 |
|---|---|
| 大きな開口部が多い | ねじれや偏心による影響 |
| 吹き抜けやスキップフロア | 水平剛性が不足することによるせん断伝達の影響 |
| リビング・ダイニング・和室等をまとめた大空間 | 大空間を構成する部材の大断面化 |
| 都市部の変形地や狭小地に建てる場合 | ねじれや偏心に加えて、塔状建物(縦横比が大きい)の場合は転倒の影響 |
※住宅だけでなくすべての建築構造物に当てはまります。
4.構造計算書は信頼できる構造設計者に依頼しなくてはならない理由
構造設計者の役割には、構造設計(構造計算)と監理という業務があります。 構造設計は、構造計算書と構造図面の作成だけではなく、建築計画との整合性を図りながら、様々な構造種別(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等)の中からそれぞれの建物に相応しい構造(骨組)を決定することです。
これらの業務にはデザイン(建築計画含む)、コスト、構造安全性等の矛盾する与条件のバランスを考えながら専門家としての判断が求められます。 場合によっては、構造的な検討結果により建築計画を作り直していくこともあります。
これまでの解説で構造設計者がいかに建築構造物の機能・安全性を担っているかお分かりいただけたと思います。 しかし、構造計算という仕事は専門性が高く、建物が完成してしまえば骨組みなどは外からは見えなくなってしまうため、偽装されても見抜きにくいという実態がありました。
実際に2005年には、あの有名な構造計算書の偽装事件が起こってしまいました。
4-1.建築業界を震撼させた構造計算書偽装問題
構造計算書偽装問題は、元一級建築士A氏が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽装していたことによる一連の事件(2005年11月17日に国土交通省公表)のことです。 具体的には、国土交通大臣認定構造計算ソフトウエアの計算結果を改ざんし、構造計算書を偽装しました。
建物の建築確認・検査を実施した行政及び民間の指定確認検査機関は偽装を見抜くことが出来ませんでした。 そのため、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルなどが建設されることになりました。
建築確認審査の時点で偽装に気が付けなかった原因はいくつかありますが、
・構造計算の作成がコンピュータ中心になっていた
・構造計算書のA4用紙1,000枚以上というボリューム
このような点から、構造設計のチェックがしにくいという状況がありました。
構造計算書偽装問題は、人命や財産に関わるものであることから、大きな社会問題となりました。 建物の構造的な品質、安全性を確保するために最も重要なことは、信頼できる構造設計者が構造設計を行ない、構造計算書を作成することです。 つまり、信頼できる構造設計者を選ぶことが建物の安全性を守る最も確実な方法になるのです。
構造計算書偽装問題と建設費高騰の密接な関係
近年の建設費高騰には構造計算書偽装問題と密接な関係がありました。
詳しくは「建設費が高騰した背景」でまとめています。ご参考になれば幸いです。
5.まとめ
今回は、構造設計における重要な書類「構造計算書」について、その概要と必要性、そして信頼できる構造設計者の重要性についてご紹介しました。 構造計算書は、建物の安全性を確認するための重要な手段です。 たとえ住宅であっても特定の条件下においては構造計算が必要な場合があり、その判断は法的要件だけでなく設計の安全性を考慮するべきであることがおわかりいただけましたでしょうか。 構造計算書偽装事件の教訓からも、信頼できる構造設計者を選ぶことが建物の安全を守る鍵といえるでしょう。
6.この記事を監修した人
この記事は、構造設計一級建築士資格を有する、構造設計の専門家が監修しています。
コラムの関連記事
-
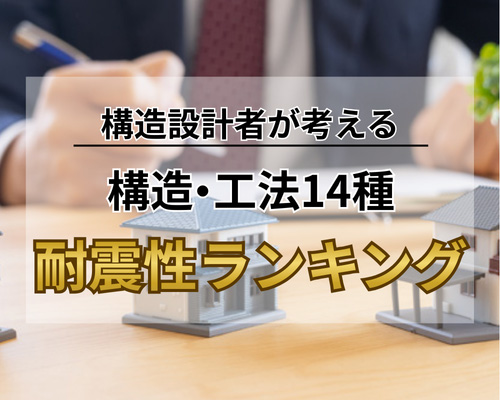
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
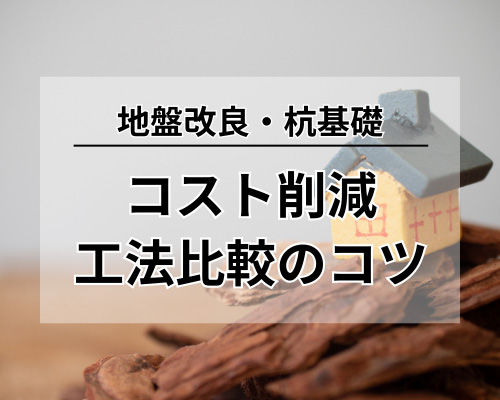
構造躯体最適化
2025年10月01日
構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...
建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...
-

メディア関連
2023年04月18日
メディア取材後の身近な反響
さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...
-

ゼロコスト高耐震化技術
2022年02月03日
構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...
2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...
RC造(鉄筋コン)の関連記事
-
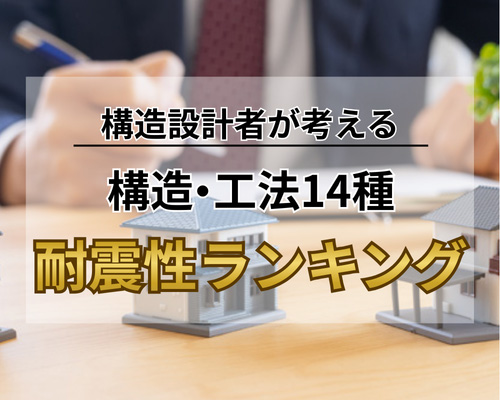
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
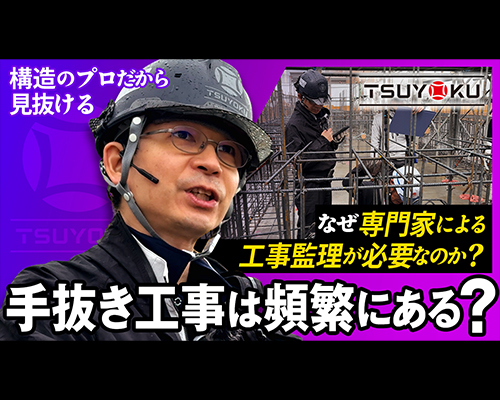
構造躯体設計監理
2025年05月26日
【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」...
『【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」によ...
-
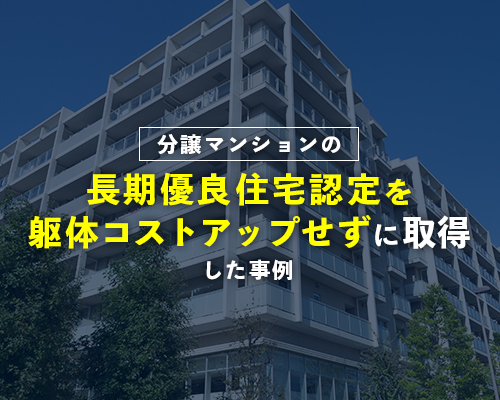
構造躯体最適化
2025年04月24日
「分譲マンションの長期優良住宅認定を躯体コストアッ...
構造躯体コストを上げずに、長期優良住宅認定を取得できた事...
-
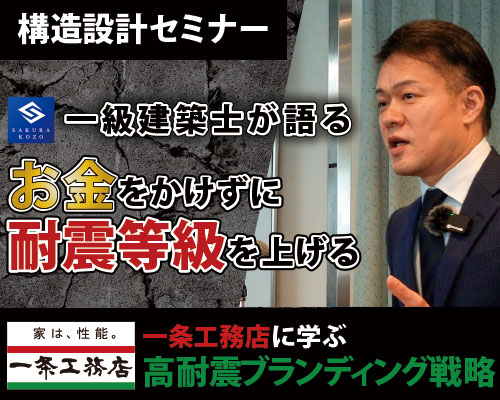
構造躯体最適化
2024年10月22日
マンション分譲研究部会セミナー「構造躯体コストを最...
東京で開催された【一般社団法人全国住宅産業協会 マンショ...
WRC造(壁式)の関連記事
-

自社工法
2026年01月09日
壁式の間取りはこれで完璧!集合住宅モデルプラン集【...
ダウンロードする 弊社には、壁式工法の制約を克服した【4...
-
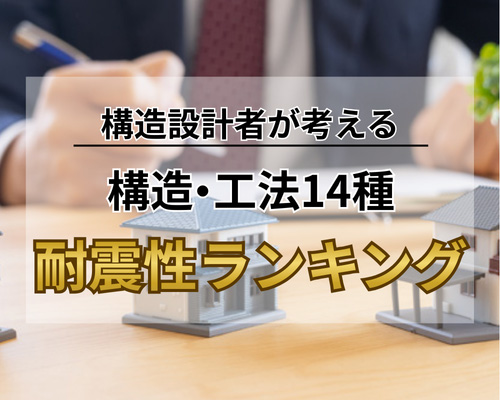
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
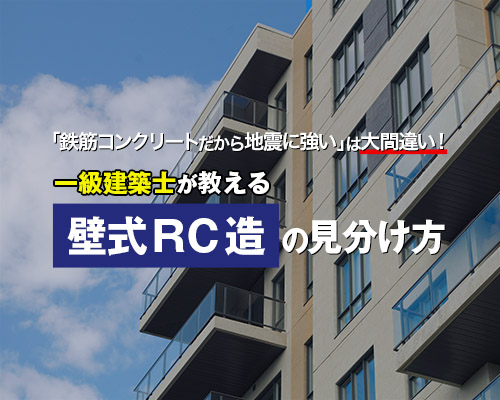
自社工法
2025年06月30日
【暴露シリーズ】鉄筋コンクリート造は地震に強くない...
多くの方が抱いている「鉄筋コンクリート造(RC造)はすべ...
-
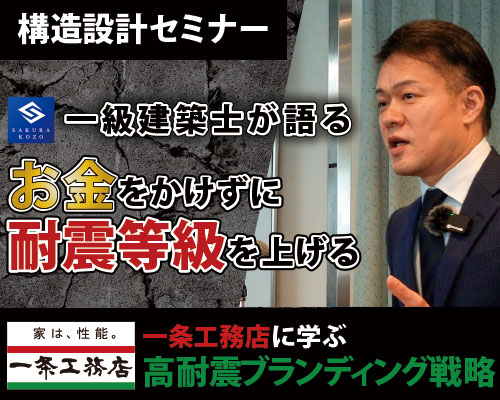
構造躯体最適化
2024年10月22日
マンション分譲研究部会セミナー「構造躯体コストを最...
東京で開催された【一般社団法人全国住宅産業協会 マンショ...
S造(鉄骨)の関連記事
-
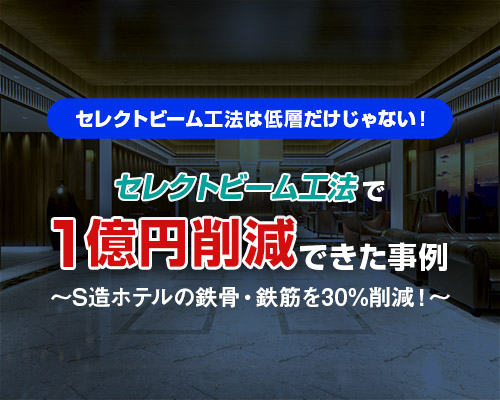
構造躯体最適化
2026年01月30日
9階建て鉄骨造ホテルの鉄骨・鉄筋量を30%削減!1...
ダウンロードする 建築コストを大幅に削減できる「セレクト...
-
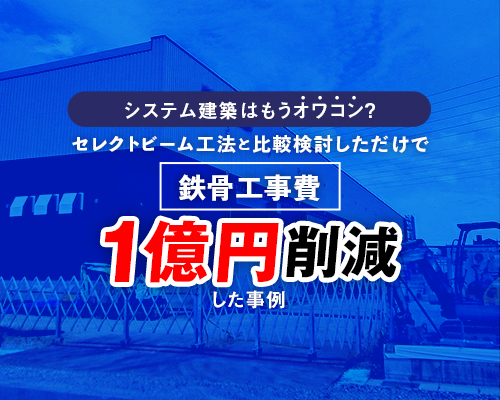
構造躯体最適化
2025年12月01日
「システム建築=最安」はもう古い!S造工場で鉄骨費...
システム建築工法で思ったよりコストが落ちなくてお困りの方...
-
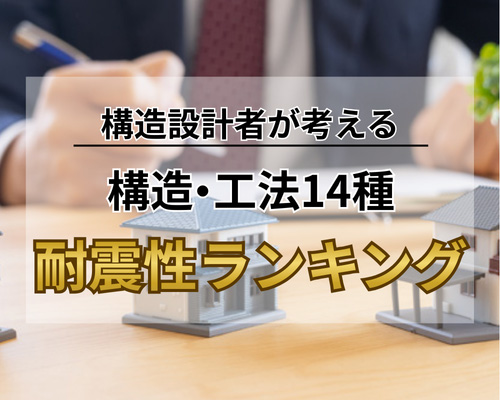
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
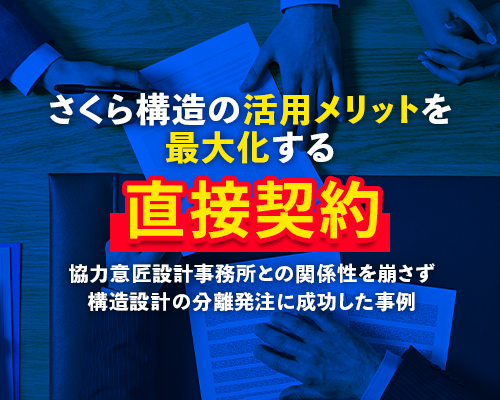
構造躯体最適化
2025年11月19日
構造設計を分離発注したいお客様必見!リスクゼロでさ...
さくら構造を意匠設計事務所の下請けとしてではなく、お施主...
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
| ●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
|---|
| ●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
|---|
| ●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
|---|




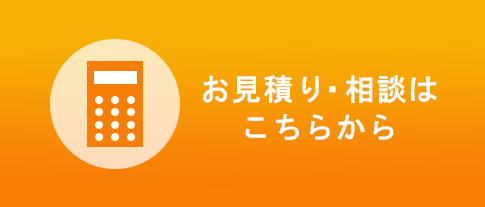

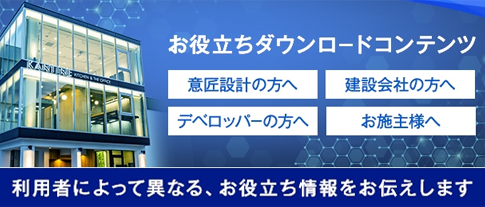
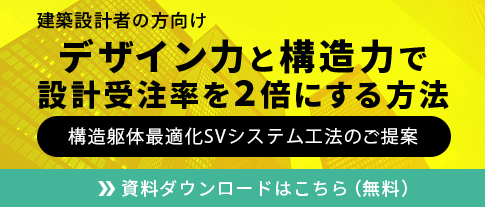
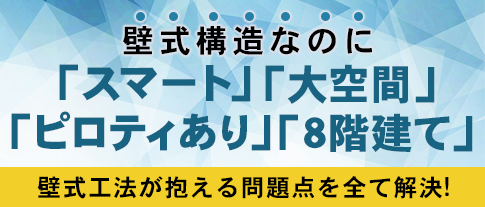
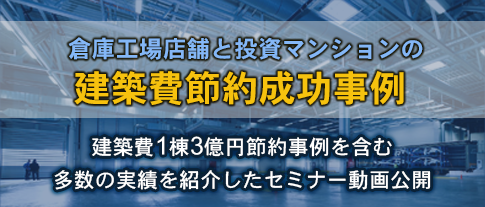
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。