建築構造とは?
この記事では、建築構造についての基本的な考え方をご説明します。
建築とは、建築物をつくる人間の行為あるいはその行為によってつくりだされた建築物のことです。 もう少し踏み込んだ言い方をすると、人が快適な生活ができ、生命・健康及び財産を守るための空間を提供する場所ということになります。
その場所で、人が快適な生活をできるための骨組が「建築構造」であり、建物を地上や地下で安全に支える構成要素です。
建築構造は、骨組の中の力の流れ、骨組の形式、材料や架構の作り方によって、様々なバリエーションがあり、これらのすべての要素を含んでいます。 つまり建築構造とは、建築物を構成する構造形式や構造材料などの総称になります。
1.建築構造を検討する前に理解しておきたいこと
建築構造の役割は、内外から建物に作用する力に対して建物が崩壊しないように建物を保つことです。 内側から建物に作用する力は、常に建物に作用している固定荷重・積載荷重があり、これらは重力に起因するものです。 この他に、自然界から一時的あるいは短期的に作用する外乱があります。 この外乱は建物に大きく影響を与え、建物が損傷したり人間や家財に被害が及ぶと“災害”となります。 外乱として考えられるものとして、地震、台風、積雪があります。
1-1.地震をはじめとする外乱
建物の安全性を考える中で最も影響が大きいのが、地震です。 地震によって建物が揺すられることで倒壊、損傷などの被害が生じます。 また、津波による建物倒壊や流失の被害、地盤の液状化による被害も発生します。
また近年、台風が日本を直撃することにより、その被害が多くなってきています。 台風の進路や規模などは予測されるようになってきていますが、その風圧力により屋根や外装材に被害を受けます。 また、大雨にともなう土砂災害により、建物を支えている地盤そのものが被害を受けることもあります。
降雪は確率的な荷重として把握されていますが、ときおり過去の統計から推測できないような積雪により被害が生じることがあります。 この他にも竜巻による被害が発生していますが、予測や対応はほとんどできていません
地震や台風など、建物に作用するこれらの力は、最終的に地盤によって支えられます。 すなわち、地盤の強度(地耐力)も大変重要な要素だということです。 「建築構造を検討する」という言葉を言い換えるなら、建物に作用する力を、いかにスムーズに、構造に大きな負担をかけずに、地盤まで伝達するかを考えること。 つまり、骨組から地盤まで伝わる力を把握することだといえます。
構造設計業務の一連の流れについて
さくら構造が実際にご依頼を受けた際に、どのような流れで構造設計業務を進めているかは「さくら構造の仕事の進め方」でまとめています。ぜひ、あわせてご覧ください。
2.建築構造は構造形式と構造材料に分けられる
建築構造は、建築物を構成する要素の総称だと説明しました。 建築構造を分解すると、骨組の構造システムと、その部材に使用する材料に分けることができます。
「構造形式」と「構造材料」を簡単に整理してみました。
| 構造形式 | 建築物に作用する力の伝達機構(構造システム)です。 純ラーメン構造、耐震壁付ラーメン構造、ブレース構造、トラス構造、壁式構造、シェル構造などです。 |
|---|---|
| 構造材料 | 建築物の構造部材に使う材料のことです。 鉄筋コンクリート、鋼、木、アルミ等があります。 |
ここからは構造形式と構造材料の種類について、さらに詳しく説明していきます。
2-1.構造形式とは?一般的な構造形式の特徴
建物の「構造形式」は、特殊な構造を含めるとその種類は無数にあります。 しかし、基本的には柱と梁を主体とした「柱梁構造」と、面材を主体とした「壁構造」に分けられます。
一般的な構造形式の特徴
| 構造形式 | 図 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 純ラーメン構造 |  |
柱と梁、床板のみで構成され、それらをつないで建物を支える仕組み。 | プランニング(平面計画)の自由度が高く、柱及び耐力壁以外は間仕切りとし、窓の配置も自由になります。 主に中高層マンションで採用されています。 |
| 耐震壁付ラーメン構造 | 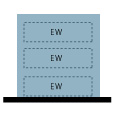 |
柱と梁、壁板を組み合わせて建物を支える仕組み。 | 耐震壁が効果的に地震に抵抗するため、柱・梁の部材寸法をある程度小さくできます。 |
| ブレース構造 |  |
柱でも梁でもなく、斜めになっている部材がブレース。このブレースにより地震や風の力に抵抗する仕組み。 | 筋交のある面を一定間隔で配置しなければならないのでプランニングに制約があります。 商業施設等で採用されています。 |
| トラス構造 | 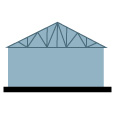 |
部材の両端がピン接合で、部材同士を三角形につなぎ合わせた仕組み。 | 外力を加えても軸力しか発生しません。 部材は曲げモーメントよりも軸力で伝える方が効率的になります。 この性質を活かして、大空間構造(体育館やドーム)や、橋梁に採用されています。 |
| 壁式構造 |  |
柱と梁の代わりに耐力壁で建物の荷重を支える仕組み。 | ブレース構造のブレース以上に構造壁の配置が重要になります。 かつ、その壁は開口などの位置が制限されます。 主に5階建て以下の低層マンションで採用されています。 |
| シェル構造 |  |
卵の殻のような曲面状の薄い板を用いた仕組み。 | 卵の殻が比較的薄い構造にもかかわらず、外力に対し強く、こわれにくい性質を活かした構造です。 |
2-2.構造材料とは?主な構造材料の特徴
建物の「構造材料」には、場面に応じたさまざまな材料が利用されています。 例えば、高層ビルのような建物では「鋼材」が用いられます。 なぜかというと、高層建物に重量が重い材料を使った場合、構造的に不効率かつ不経済となってしまうからです。 そのため、高層建物には軽くて強い鋼材が好まれます。
一方で、一般的な住宅では日本より古くから用いられている「木材」が主流です。 また、マンションのような遮音性や集合住宅としての機能性を確保しなければならない建物の場合は「鉄筋コンクリート」を用います。
下表のように、材料にはそれぞれのメリットとデメリットがあります。 材料性質のメリット・デメリットをよく理解し、設計に活かすことが重要になります。
主な構造材料の特徴
| 構造部材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 鋼材(鉄) |
|
|
| 木材 |
|
|
| 鉄筋コンクリート |
|
|
| アルミ |
|
|
構造躯体を最適化する工法について
さくら構造は、構造形式や構造材料の特性を活かした自社工法を開発しています。
詳しくは「構造躯体最適化工法」をご覧ください。
3.建物構造の安全性は構造体以外の要因にも注意
建築の安全性を論じるとき、構造体のみに注目されることが多いようです。 しかし、近年の地震被害では天井材等の非構造部材の損傷による落下、さらには仕上げ材、家具の転倒などによって引き起こされることも多くなっています。
そのため、建物全体としての安全を考えることが必要であり、建物側での配慮以外にも、家具や什器の転倒防止の対策を行うことにより実質的な安全の確保ができます。
構造形式と非構造部材、仕上げ材の安全性とは関連が深いです。 例えば、鉄筋コンクリート壁式構造のような強度型の建物は、地震時の変形が少ないことが長所です。 しかし、一方で応答加速度は大きくなる傾向があります。
S造(鉄骨造)のような靭性型はその逆で、応答加速度は若干減りますが水平変形が大きくなります。 応答加速度が大きければ家具の転倒などが生じ、水平変形が大きければ非構造部材、仕上げ材の損傷に繋がります。 つまり、構造形式の選択と非構造部材の耐震安全性確保の条件が関連していることになります。
4.まとめ
今回は、建築構造の基本的な考え方と、それに関連する構造形式および構造材料の特徴と選定のポイントについてご紹介しました。 「建築構造」は、「構造形式」「構造材料」に大きく分けられ、さらにそれらと非構造部材を含めた安全性確保の考え方は様々です。 最適な答えを探すには設計者の技量、経験、倫理観によるところが大きく、多くの条件をバランスよく取り入れ、安全性に配慮した建物を設計する。 それこそが、構造設計者の役割になります。
5.この記事を監修した人
この記事は、構造設計一級建築士資格を有する、構造設計の専門家が監修しています。
コラムの関連記事
-

メディア関連
2023年04月18日
メディア取材後の身近な反響
さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...
-

ゼロコスト高耐震化技術
2022年02月03日
構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...
2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...
-

構造躯体最適化
2021年04月02日
倉庫・工場・店舗・体育館をローコストで実現する注意...
(1)から(4)に渡り、機能性・経済性を最優先すべき「物...
-

構造躯体最適化
2021年04月02日
システム建築と在来工法の比較③ ―工事業者選定編―
前回に引き続き、機能性・経済性を最優先すべき「物流倉庫や...
RC造(鉄筋コン)の関連記事
-
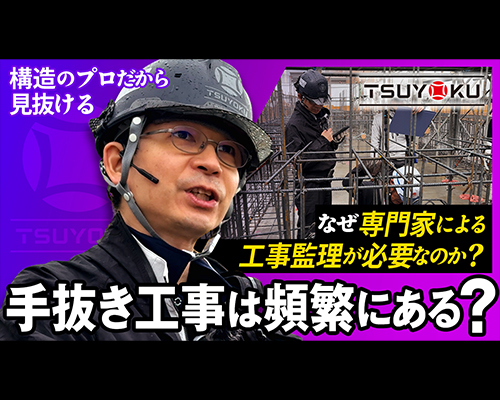
構造躯体設計監理
2025年05月26日
【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」...
『【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」によ...
-
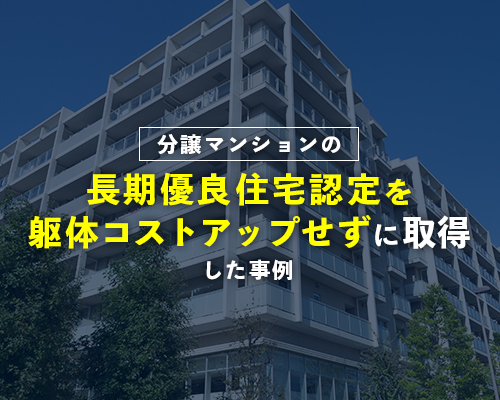
構造躯体最適化
2025年04月24日
「分譲マンションの長期優良住宅認定を躯体コストアッ...
構造躯体コストを上げずに、長期優良住宅認定を取得できた事...
-
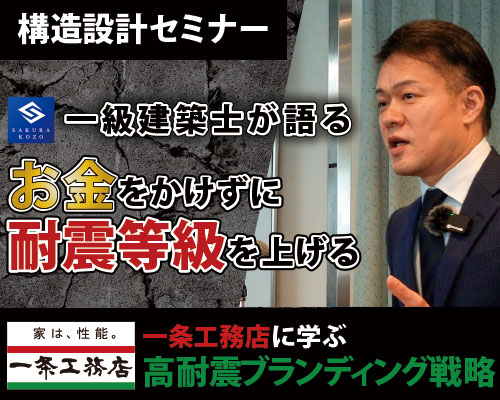
構造躯体最適化
2024年10月22日
マンション分譲研究部会セミナー「構造躯体コストを最...
東京で開催された【一般社団法人全国住宅産業協会 マンショ...
-
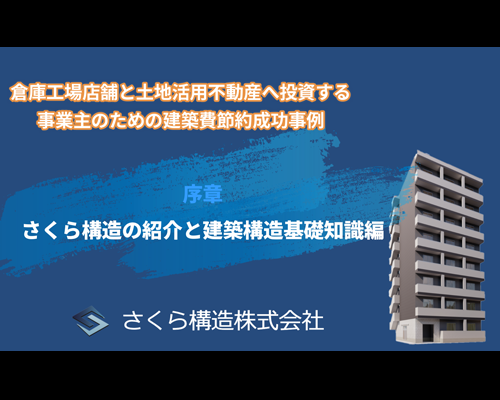
構造躯体最適化
2021年12月22日
倉庫工場店舗と土地活用不動産へ投資する事業主のため...
2021年12月7日(火)に東京ビックサイトで開催された...
WRC造(壁式)の関連記事
-
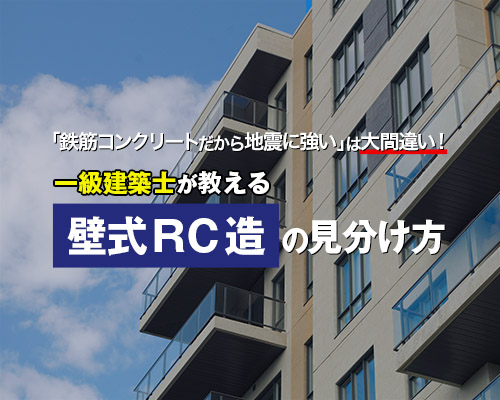
自社工法
2025年06月30日
【暴露シリーズ】鉄筋コンクリート造は地震に強くない...
多くの方が抱いている「鉄筋コンクリート造(RC造)はすべ...
-
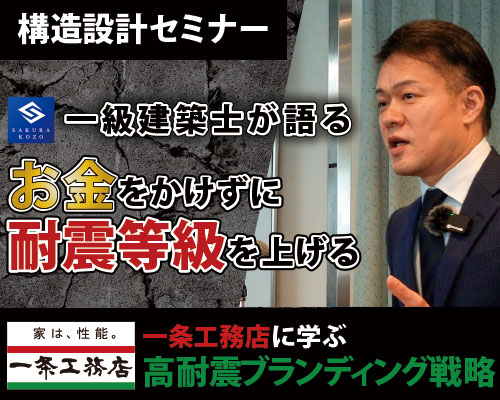
構造躯体最適化
2024年10月22日
マンション分譲研究部会セミナー「構造躯体コストを最...
東京で開催された【一般社団法人全国住宅産業協会 マンショ...
-
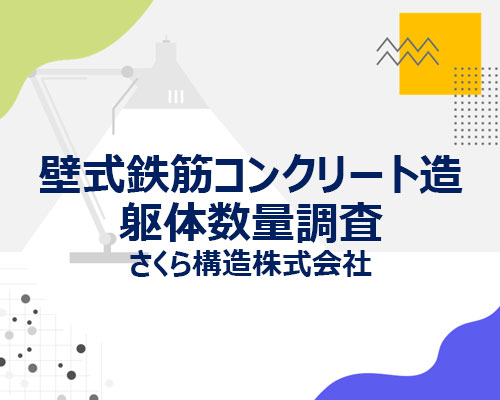
自社工法
2024年01月22日
壁式鉄筋コンクリート造躯体数量調査
壁式鉄筋コンクリート造は、 「柱梁型がなく、意匠的には好...
-
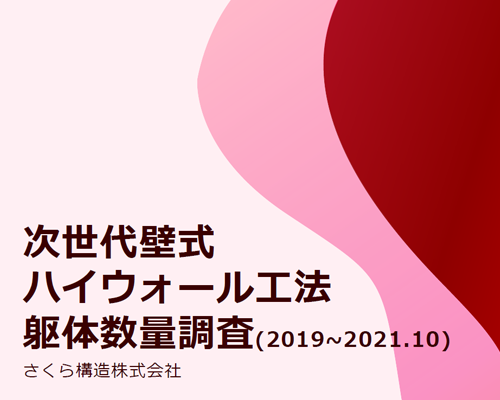
構造コンサルティング
2021年12月28日
次世代壁式ハイウォール工法躯体数量調査(2019~...
壁式構造は、 「柱梁型がなく、意匠的には好ましいが…」 ...
S造(鉄骨)の関連記事
-
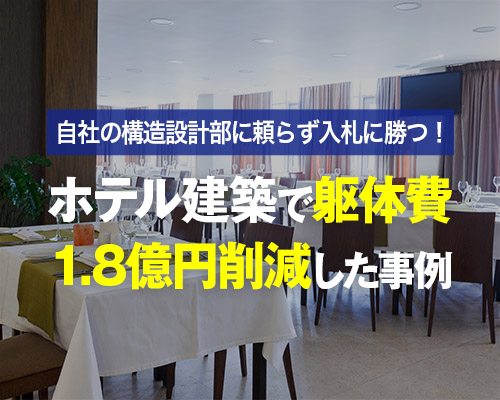
構造躯体最適化
2025年06月20日
自社の構造設計部に頼らず入札に勝つ!ホテル建築で躯...
ある建設会社の札幌支店様が、東京本社に構造設計部があるに...
-
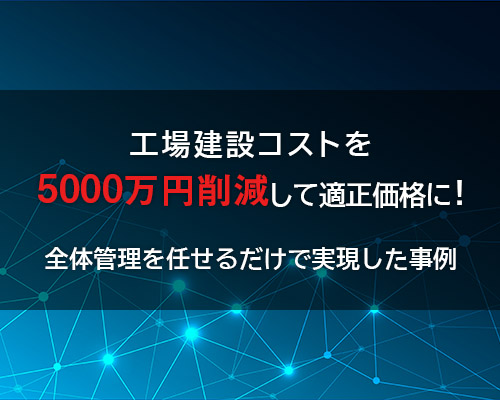
構造躯体最適化
2025年03月10日
「工場建設コストを5000万円削減して適正価格に!...
懇意にしているゼネコンがいるため、建設会社を変えずに建築...
-
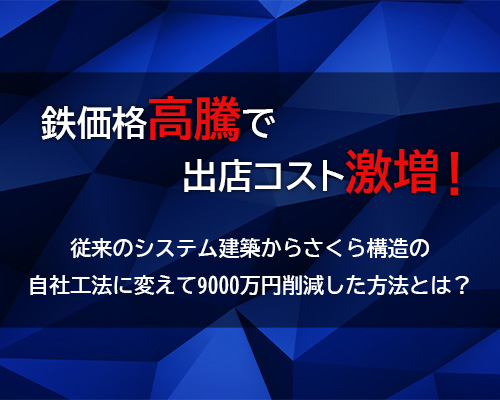
構造躯体最適化
2024年11月11日
鋼材価格高騰で出店コスト激増!「9000万円削減」...
鋼材価格の高騰により出店コストが増えてお困りの事業主様が...
-
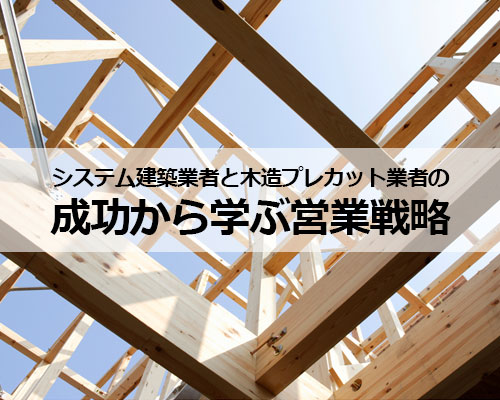
構造躯体最適化
2024年01月16日
システム建築業者と木造プレカット業者の成功から学ぶ...
システム建築業者が成功した要因は、建設会社の受注率向上と...




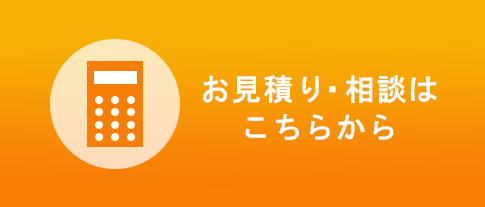

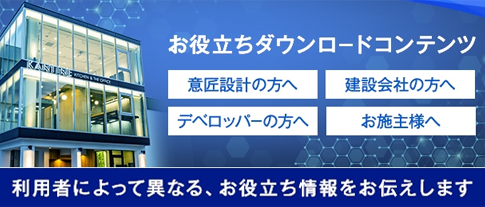
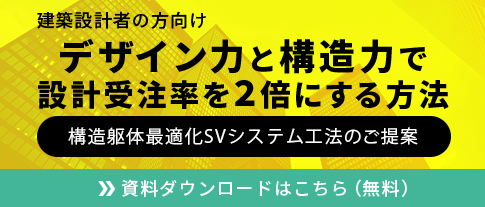
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに5000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。