耐震強度偽造-姉歯(あねは)建築設計事務所


今回の偽造の内容
確かな情報ではないですが・・・
・地震力を約半分にした(地域係数を0.5にした?)
・建設コストは約1割減(人命失うリスクを高めて建設費はたった1割の建築躯体コスト最適化)
・震度5強で倒壊の可能性がある。
(通常は震度5強~6弱では損傷しない事で地震後そのまま補修をしなくても建物として使える、震度6強~震度7では倒壊しない事で地震後そのまま建物を使用出来ないが最悪でも人命を守る事が出来る)
・構造計算の電算機出力を偽造し、地震力を通常に入力した計算出力と地震力を半分にして入力した計算結果の出力を、合体させて審査機関に提出した。
構造設計をめぐる環境
おそらくここ数日のアクセスを見る限り建築業界以外の方の訪問がかなり増えていると思いますので、現在の構造設計の仕事がどのように発生し誰が、誰に仕事を依頼しているのか、また構造技術者が設計現場の中で、どういう立場にあるのかとう言う基本的な事を少し説明します。
・ケース1
施主(建築主)→意匠設計事務所等→構造専門設計事務所
・ケース2
施主(建築主)→意匠設計事務所等
→構造専門設計事務所
※意匠とはデザインとか間取りを考える設計の事です。
ケース1の場合、構造技術者(構造屋)は施主(建築主)から直接仕事をもらいません。
あなたが家を建てる時まず誰に仕事を頼むか考えて見てください。
ハウスメーカー・工務店・建設会社・意匠設計事務所と色々ありますが、構造技術者は上記の企業のどこにも存在していません。
ほとんど企業内部の中に構造技術者は雇ってないのです。超大手さんは別ですが。
通常はこれら企業が工事案件が決まった段階で設計図を書き、それを元に我々構造技術者に構造計算の発注(外注)を行います。
したがって、意匠事務所等やハウスメーカーを交いして仕事の依頼が来ますので我々構造技術者は施主(建築主)の顔を全く知らずに仕事を行います。
ケース2の場合は、施主が直接、意匠事務所と構造事務所別々に仕事を発注する場合です。
「企業」「デベロッパー」「官公庁」等の場合が多いと思います。
この場合は施主と構造技術者とが直接顔をあわせて技術的な打ち合わせを行う事があります。
ある程度定期的に建物を建て、施主側に建築の知識がある場合に採用されます。
ケース2もデベロッパーが施主の場合、その後マンションを建設し一般消費者に販売すれば、買った消費者が建物の所有者になります。
ケース1もケース2も共通して言える事は構造技術者と実際にその建物の所有者となり居住する人とが直接接点が無い事があります(企業や官庁は別ですが)。
だから一般消費者は我々構造設計者の存在すら知りません。
建築の設計と言えば、TVのリフォーム番組の「匠」みたいな人や「建築家」みたいな人を思い浮かべるようです。
みな自分と家族の命を守るべき建物の耐震設計に全く興味を持たずに数千万ものお金を費やしているのです。
例え耐震に少し興味を持っても我々構造技術者の存在までは、まずたどり着きません。
工法や技術的な部分の勉強はするかもしれませんが、技術を実際に使い、安全な建物を設計する”人”には興味を持つことはありません。
もしくはデザインをやっている意匠設計者が構造計算もやっていると勝手に思いこんでいるかです。
ネット上を見てください。構造技術者でそれなりのサイトを運営している人はほとんどいません。
ちょっとした構造事務所は自分の会社のサイトを持っていますが、自社宣伝のためのサイト作りしかしていません。
一般消費者に情報発信しているのは意匠設計をやっている建築家たちです。
そして彼らが構造の部分の情報も発信しています。
これでは、消費者が我々の事を知らないのも無理はないでしょう。
我々にとってのお客はたいていの場合末端の消費者でなく、同じ業界内のメーカーや建設会社・設計事務所・デベロッパー等です。
確認審査が民間になった事に問題がある?
どうもテレビ報道やWEBサイト・ブログなどでは建築確認審査が民間業者に移行した事自体にも原因がある。
といったような表現が見受けられます。
しかし、私はそうは思いません。
はっきりいいますが、お役人の方々が確認審査をしていた一昔前と、民間業者がメインになりつつある現在とで、確認審査をする人の技術レベル・審査内容にそれほど大きな差は感じられないからです。
逆に民間に委託されるようになってからの方が技術的な質疑や審査が多くなり、それなりに建築構造を知っている方が審査をしているなと感じる事もありました。
考えてみてください。
公務員試験に受かっただけ人が耐震設計とか構造設計とういう特殊な仕事を実務経験無しに、構造審査をまともに出来ると思いますか?
一度も自分で構造計算をやった事もない人が審査官であったりする事などは、珍しい話ではありません。
そして、こういう現実は民間業者が確認審査を始めるずっとずっと前からの話です。
表には出ていませんが、民間の確認審査期間が無かった時代にもこういった不正が少なからずあったと思います。
たまたま今回、血迷った構造設計者が幼稚で低レベルな不正を行ったために判明してしまった。また民間確認審査機関が正直だったからその事実を公表した。
民間確認審査機関も自分のチェックミスを素直に認めない所はよろしくないと思いますが、不正に気づき、公表した事は評価できます。
不正に全く気づかずにほったらかしにしている審査機関よりもずっとましだと思うからです。
では今回の審査が適正だったかと言えば、適正でなかったから見逃したのですから適正とは言えないでしょう。
ただその現実は今はじまった話ではないのです。
表に出ない不正な構造計算が数多くあるだろうと思うからこそ、今回不正に気づき公表しただけでも「まだ・ましな方」と表現してみました。
といっても、あくまで「まだ・ましな方」としか言えないのですが。
根本的な問題
私は構造設計の現場にいる人間として、今回の問題が一部の悪人がしでかした悪さという問題で終わらすにはあまりに深い問題を抱えている気がします。
一つだけ例をあげます。今回姉歯氏は地震力を半分にして建物を設計しました。
そこに工学的判断は全く無く、彼は「偽造」と言う最悪方法を選択しました。
しかし、今現在偽造と言う手法以外の方法で地震力を約半分にして設計している建物があります。
偽造でないので法律違反ではありません。
工学的判断に基づいて、計算手法を変えるとこのような事が出来てしまいます。
構造計算とは、設計者が考えた、いくつもの仮定に仮定を重ねて、計算してみたらこうなった。
といったような物で、設計者が工学的判断に基づいて最初に考える仮定や計算手法を変えれば、偽造などしなくても、計算結果をある程度誘導できてしまいます。
そして、そこには危険な建物を造らないと言う構造技術者のモラルや良心と言う、とても技術とはかけ離れた、人間くさい部分によって今の構造設計が保たれている現実が見てとれます。
こういった話は本当に一部の技術者の間でこっそりと、この問題を協議していたりします。
まったく表には出てきません。
デベロッパーも建設会社もどんどん設計地震力の小さな建物を建てています。
もちろん今もです。
どうでしょう。私が今回の問題は一部の血迷った構造技術者の起こした事件とは言えないの言う意味が少し伝わったでしょうか。
建築業界の閉鎖感と建築システムの問題、そして消費者の無知。
この事実が今回の事件の根底にある気がしてなりません。
結局だれが悪い?
どこかの国の逸話でこんな話を聞いた事があります。
構造技術者は自分が設計した橋(ブリッジ)が完成したら、まず最初に設計者自身が橋の下に立った状態で、その橋の上を戦車で走行させるそうです。
もちろん設計ミスをしていて橋が壊れれば橋下の設計者は怪我どころでは済まないでしょう。
これはちょっと大げさな話だとは思いますが、今日の日本では構造設計についての責任が非常に曖昧になっている気がします。
一つ例をあげると・・・
車を買って、不具合が出た時「下請けメーカーのミスだから下請け業者に言って」なんて自動車メーカーが言ったら、そんな会社の車はもうだれも買わないでしょうし、大問題になりますよね。
普通は自動車メーカーが問答無用で消費者に対して無料修理や引き取りなどの責任を負うでしょうし、それが当たり前という認識があります。
発注者側の責任
意匠設計・構造設計を外注した企業は「我々は関与してない」とか言ってるが、関与してないって事は設計責任者である発注者自信がノーチェックだったか、構造計算の内容を見てもさっぱりわからなかったかのどちらかで、結局建物を設計し監理する能力が欠如していたとさらけ出しているようなものです。
今回は偽造した事に大きな問題があるが、偽造はしてなくてもミスをしてしまうケースもある。
つまり偽造が見抜けないならミスも見抜けないでしょう。
偽造(ミス)をしたのが下請けだから下請けが悪い?
お金を出している消費者に対してそんな理屈が通用するわけがありません。
消費者は元請けである企業と契約してお金を払っているのだから、契約した企業に責任をとってもらいたいと思うはずです。
直接にしろ間接的にしろ、構造計算を依頼(外注)した側の責任は重大です。
一般消費者にとっては構造設計者の顔も名前もしらずに購入した人がほとんどでしょう。元請けの企業を信用してマンションを購入したんですから。
確認審査機関の責任は、ニュースや他のサイトでさんざんたたかれているので、ここでは省略します。
悪いのは事実です。
なにがしかの審査対策が必要なのは間違いありません。
施工業者にも大きな責任があります。
今回は施工業者も色々と疑われているようですが、極端に鉄筋が少なかったり、柱が小さければ普通は気づきます。
施工者は工事を請け負い、これはおかしいと思った場合は必ず設計監理者に報告し確認をする義務がある事を建設業法で決められているからです。
これを怠ればやはり法律違反になります。
しかし、まともな建設会社は「これはあやしい」と思えば請負契約を絶対にしません。他の構造屋にチェックをしてもらい大丈夫な場合のみ仕事を受ける等、自社で対策をしているまじめな建設会社もたくさんあります。
施工会社は事件に関与していようがいまいが、責任がある事はあきらかです。
消費者側の問題
普段の買い物で無農薬がいいとか言って野菜選びをしたり、産地や作り手を気にして買い物をしている方は結構多いと思いますが、自分と家族の命に直接関わり、また資産価値の面でも非常に重要な建物の耐震性を本気で考えないで数千万の買い物をするその感覚。
あきらかに、その価値観をあらためた方がいい事に、消費者のみなさんは気づくべきです。
業界のシステム自体に問題があるのでは?
今回事件の本人である姉歯氏も、もし仕事をもらっている相手が実際にその建物に住む住人であったなら、こんな偽造はしなかったかもしれません。
また住人も「地震で壊れてもいいからコストを安くしろ」なんて言わないでしょう。ちゃんと仕事をして喜んでもらえる方がいいに決まっています。
実際に建物を所有し生活する施主以外のデベロッパーや意匠設計事務所等が、構造計算の仕事を外注する場合、どうしても目先の利益確保のため、建物コストを下げ安い金額で設計・販売しようとします。
安ければ売れます。
賃貸にするにしても利回りがあがります。
消費者・住人は建物の構造についてはほとんど無知ですから、そんな事を聞いてくる人はあまりいません。だいたい構造計算って言葉すら知らないのですから。
あとは確認審査を上手くごまかせれば超ローコストマンションの出来上がりです。
消費者は安く買えたと喜び、企業は儲かります。
こんな事が今までずっと行われてきたのです。
だれも気づかないから上手に手を抜いて仕事をした人が勝ちです。
まじめにやると過剰設計だ、仕事が遅いと言われ仕事が来なくなる事もあります。
・コストをやすく出来る構造技術者がいい技術者と言う風潮。
・仕事を確保するためには、仕事の発注者にとって有利な設計をしがちになる。
この問題は、ほとんどの構造技術者が感じている事で、それを技術者のモラルで突っぱねているのが現状です。
まじめに仕事をすればするほど貧乏になる。
結果、続けて行けなくなった事務所は廃業し、まじめな技術者が減っていく悪循環。
姉歯氏の事務所は一般の方が思う建築士のイメージとは、かけ離れたほどボロかった。
個人の構造事務所はみんなあんなもんです。
彼がやった事は技術者として弁解の余地がなく、人間としてあきらかに間違っていますが、企業に利用され、現在の業界システム問題の波に飲まれてしまったのだとしたら、業界自体の問題を無視する事はできないのではないかと思います。
あえて責任の重さ順に個人的判断で並べてみました。
- 0.建築業界のシステム全体の問題
- 1.当然偽造した本人
- 2.構造設計を外注した企業、
つまり元請け業者であり意匠設計者 - 3.施工業者
- 4.確認審査機関
- 5.国
- 6.消費者
あえて0番を作りました。
そして6番目に消費者も入れておきました。
かなり、思い切った事を書きすぎた気がしてちょっとビビッテいます。
苦情お問い合わせはメールでお願いします。

コラムの関連記事
-
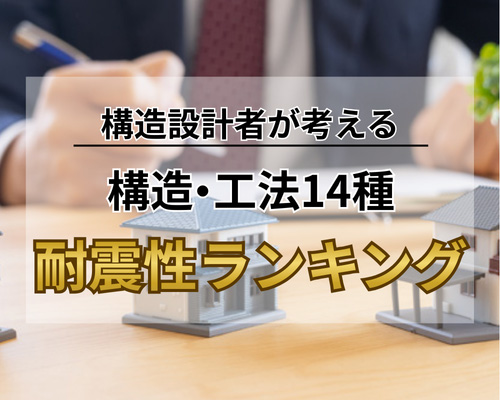
構造コンサルティング
2025年12月01日
地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...
家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...
-
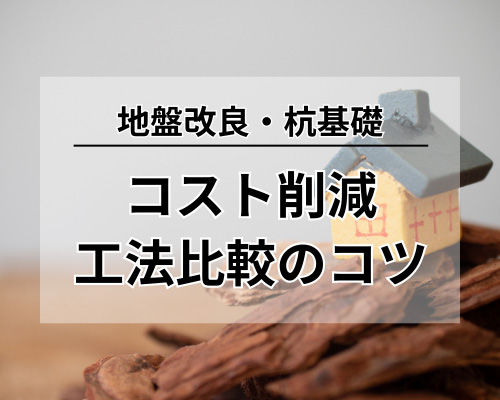
構造躯体最適化
2025年10月01日
構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...
建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...
-

メディア関連
2023年04月18日
メディア取材後の身近な反響
さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...
-

ゼロコスト高耐震化技術
2022年02月03日
構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...
2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...
建築基準の関連記事
-

定額制構造設計KozoWeb
2018年04月23日
建築構造設計に必要な資格とは?
この記事では「建築構造設計をするために必要な資格」につい...
-

超速構造設計
2018年03月30日
構造計算と構造設計の違いとは?具体的な計算方法を一...
構造は台風や地震など自然の脅威から建築を守る役割を担って...
-

定額制構造設計KozoWeb
2009年04月25日
構造設計一級建築士とは
構造設計一級建築士制度が始まりました。 構造設計一級建築...
田中 真一
-
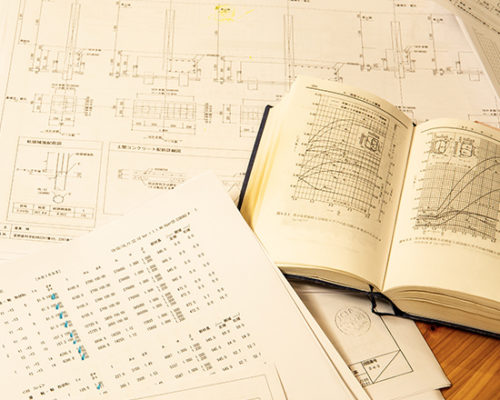
定額制構造設計KozoWeb
2009年02月28日
構造設計一級建築士とは
構造1級建築士概要 平成18年12月に公布された新しい建...
田中 真一
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
| ●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
|---|
| ●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
|---|
| ●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
|---|



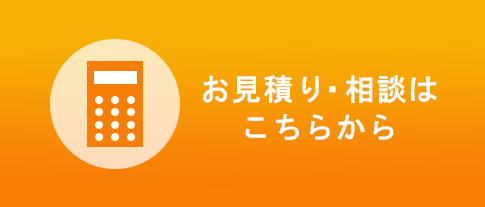

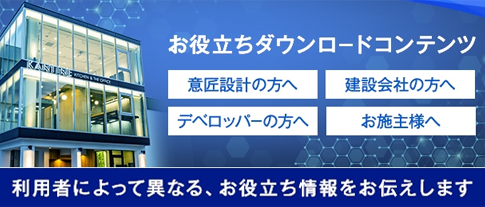
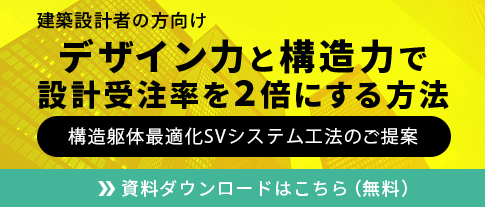
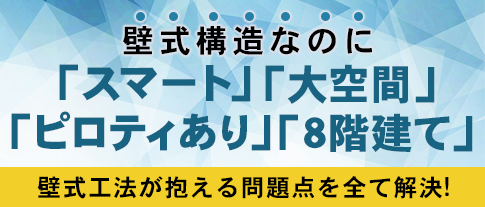
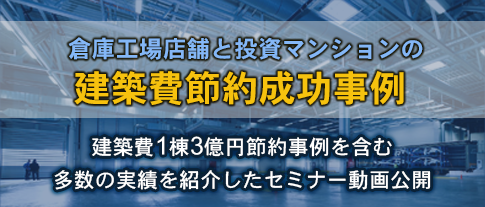
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。